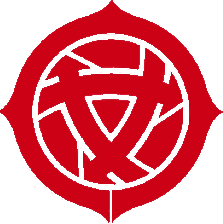関西万博×光学薄膜 Episode:2
三面スクリーンとプロジェクターが描く未来と光学薄膜の役割
1. 没入体験を支える映像の力
2025年大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、最先端の映像演出や体験型展示が数多く展開されます。その中で来場者を強く引き込む没入型映像体験を実現する要となるのがプロジェクター技術です。そして、その性能を根底で支えているのが、レンズや光学部品に施される光学薄膜(光学フィルター)です。高輝度化・高精細化とともに、光学薄膜の品質が映像の鮮明さや色再現性、耐久性に直結します。
今回の関西万博における映像技術の「凄さ」は、単なる視覚情報の提供を超え、空間そのものを再構築する手段へと進化しています。特に「没入型映像」と呼ばれる分野では、視覚・聴覚・触覚など複数の感覚を刺激することで、観る者を物語の中へと引き込み、現実と仮想の境界を曖昧にする体験が可能となっています。この没入体験を支える技術には、以下のような要素が組み合わされています。
◆3次元コンピュータグラフィックス(3DCG)
空間全体をリアルタイムで描画し、奥行きと動きを伴う映像を生成。
◆サラウンド音響システム
音の方向性と距離感を再現し、空間の臨場感を高める。
◆インタラクティブ入力技術
観客の動きや声に反応するセンサーやUIにより、映像との双方向性を実現。
◆環境演出装置
風、振動、温度などの物理的刺激を加えることで、よりリアルな体験を演出。
こうした技術は、没入型VRシステムや、複数面スクリーンを用いたなどで装置に応用されてきました。近年では、プロジェクターと特殊塗料を用いた壁面投影型のシステムなど、より簡易かつ高精度な没入環境も登場しています。2025年大阪・関西万博では、来場者を映像の中に包み込む三面スクリーン(トリプルスクリーン)+高輝度プロジェクターの演出が登場しており、前方・左右の3面に映像が広がることで、人間の視野の大半を覆い、まるでその場にいるかのような感覚を生み出します。科学映像、アート演出など、没入感を高めるさながら舞台装置としての役割を果たしています。これらの没入型映像技術が来場者の五感に訴えかける体験を創出し、未来社会のビジョンをより鮮明に伝える手段として活用され、映像はもはや「見るもの」ではなく、「入るもの」へと変貌しつつあるのです。
2. 三面スクリーンとは──プロジェクターが支える映像演出の要
今回の関西万博では、様々なパビリオンで三面スクリーンが採用されており、没入体験を楽しむことができます。韓国のような大きいパビリオンから、コモンズの中に出展されておられる国まで幅広く利用されている技術です。
三面スクリーンとは、正面スクリーンに加えて左右の壁面にも映像を投影することで、視野の約270度を映像で包み込む次世代型上映システムです。代表的な技術としては、韓国のCJ CGV社が開発した「ScreenX」があり、映画館や展示空間において圧倒的な没入感を提供しています。このシステムでは、複数台のプロジェクターが高精度に同期し、映像の連続性と空間の一体感を保ちながら、観客の周囲に広がる映像世界を構築します。特にアクションシーンや風景描写など、空間的広がりが求められる場面では、左右スクリーンが物語のスケール感と臨場感を飛躍的に高めます。技術的には、以下の要素が三面スクリーンの実現に不可欠です。
✅マルチプロジェクション制御
複数の映像ソースをフレーム単位で同期させることで、映像のズレや遅延を防止。
✅空間補正アルゴリズム
壁面の形状や反射特性に応じて、映像の歪みをリアルタイムで補正。
✅広色域・高輝度投影
左右スクリーンでも正面と同等の色再現性と明るさを維持するため、RGBレーザー光源や高性能DLPチップが採用されることが多い。
✅光学薄膜の活用
プロジェクター内部の光学系には、反射防止膜や色分離膜などの光学薄膜が用いられ、映像の鮮明さと効率を支えている。
三面スクリーンは、単なる視野拡張ではなく、空間そのものを語りの舞台へと変える技術です。プロジェクターの進化とともに、映像演出の可能性はさらに広がり、展示空間や教育、エンターテインメントの分野においても応用が進んでいます。
3. 万博で実際に三面スクリーンが見られる代表的なパビリオンは?
2025年大阪・関西万博では、三面スクリーンを活用した没入型映像体験が、複数のパビリオンで展開されています。その中でも特に注目されるのが、韓国パビリオンです。韓国パビリオンでは、未来社会をテーマにしたミュージカル作品が、三面の大型マルチスクリーンに映し出されます。物語は、祖父が残した未完成の楽曲を孫娘が2040年の未来で完成させるというもので、K-POPの音楽とダンスが融合した映像演出が展開されます。三面スクリーンにより、観客は物語の舞台となる未来都市の中に入り込んだかのような感覚を味わうことができます。高精度マルチスクリーン同期技術を使い、3面にわたる映像をフレーム単位で同期させ、視覚の連続性を確保し、抜群の没入体験ができます。
また、アメリカ館では巨大LEDスクリーンによる宇宙探査体験が提供されており、床の振動や音響効果を組み合わせた没入型演出が話題となっています。三面スクリーンとは異なる形式ながら、空間全体を映像で包み込むという点では共通しており、万博全体が「映像空間の実験場」として機能していることがうかがえます。
このように、三面スクリーンは単なる映像演出を超え、物語と空間を融合させるメディアとして、万博の体験価値を大きく引き上げています。来場者は、未来社会のビジョンを「見る」のではなく、「体験する」ことになるのです。
4. 三面スクリーンを実現するプロジェクターにおける必要な光学薄膜は?
三面スクリーンの没入体験を支えるプロジェクターには、極めて高度な光学性能が求められます。特に、複数面への高輝度・高精細な映像投影を安定的に行うためには、内部の光学系に用いられる「光学薄膜」が重要な役割を果たしています。
色分離・合成を担う干渉薄膜
プロジェクターのフルカラー映像は、白色光をRGBの三原色に分離し、それぞれの映像を形成した後に再合成することで実現されます。この色分離・合成には、光の干渉性を利用した「ダイクロイック膜(干渉フィルター)」が不可欠です。
🟩高精度な分光特性により、色の境界を明確にし、不要光の混入を防止。
🟩波長ごとの透過率・反射率を制御することで、色再現性と輝度を両立。
反射防止膜(ARコーティング)による光効率の向上
光学系の各レンズやプリズム表面では、屈折率の違いによって反射が発生します。これにより光の損失やゴーストが生じるため、反射防止膜が施されます。
🟩Ion Assisted Deposition(IAD)方式により形成された高密度膜が主流。
🟩多層構造により広帯域での反射率低減を実現し、明るさとコントラストを向上。
高輝度化に伴う熱対策──TDCM(温度補正機構)
三面スクリーンでは、広範囲にわたる高輝度投影が求められるため、プロジェクター内部での発熱が大きな課題となります。特に投射レンズでは、温度変化による焦点ズレや結像性能の劣化が懸念されます。
🟩TDCM(Temperature-Dependent Correction Mechanism)により、温度変化に応じて光学特性を動的に補正。
🟩熱膨張による光路の変化をリアルタイムで補正し、安定した映像品質を維持。
レーザー光源との融合
近年では、RGBレーザー光源を用いたプロジェクターが主流となりつつあります。これにより、より広い色域と高輝度が実現されますが、レーザー光の干渉性が高いため、光学薄膜の精度が一層重要になります。
🟩レーザー光に対応した反射防止膜や色分離膜の開発が進行中。
🟩ナノレベルでの膜厚制御により、波長シフトや干渉ノイズを抑制。
このように、光学薄膜はプロジェクターの性能を根幹から支える技術であり、三面スクリーンの没入体験を成立させるための不可欠な要素です。映像の「美しさ」と「安定性」は、目に見えない膜の精度によって決まると言っても過言ではありません。
5. 三面スクリーンとプロジェクターが家庭に導入される未来は?
三面スクリーンによる没入型映像体験は、現在では映画館や展示施設など限られた空間でのみ実現されています。日本国内でも「ScreenX」導入劇場は2025年時点でまだまだこれからです。対応作品の少なさや設備コストの高さが普及の障壁となっています。しかし、技術の進化とライフスタイルの変化により、三面スクリーンの家庭導入は現実味を帯びつつあります。
✅ 技術的可能性──小型化・高性能化の進展
•超短焦点プロジェクター:壁から数十センチの距離で大画面投影が可能。左右壁面への投影も現実的に。
•折りたたみ式スクリーン構造:軽量素材(スチレンボードやダンボール)を用いたDIY型三面スクリーンの構築ガイドも登場。
• AIによる映像補正:壁面の形状や色に応じて映像をリアルタイムで補正する技術が進化中。
これらの技術により、従来は専用施設でしか体験できなかった三面映像が、一般家庭でも再現可能な水準に近づいています。
✅ 普及への課題──コスト・コンテンツ・空間
•高性能プロジェクターやスクリーン素材の価格が依然として高く、導入には一定の投資が必要。
•三面対応コンテンツの制作には特殊な編集工程が必要で、現時点では対応作品が限定的。
•一般家庭の間取りでは、左右壁面の確保が難しいケースも多く、設置環境に制約がある。
✅ 未来展望──家庭での映像空間体験へ
今後、メタバースやXR(Extended Reality)との融合により、家庭内での映像体験はさらに進化する可能性があります。三面スクリーンは、単なる映画鑑賞を超えて、教育・医療・遠隔会議・ゲームなど多様な分野での応用が期待されています。また、プロジェクター市場ではRGBレーザー光源やMEMSミラーによる空間投影技術が進化しており、壁面そのものをスクリーン化する「壁面一体型映像空間」の実現も視野に入っています。三面スクリーンは、家庭における映像体験の新たなスタンダードとなる可能性を秘めており、今後の技術革新とコンテンツ開発の進展がその鍵を握っています。
6.さいごに
かつて日本は、液晶プロジェクターやDLP技術の黎明期において、世界をリードする開発力と製品力を誇っていました。エプソン、ソニー、三洋電機などが生み出した高性能プロジェクターは、教育・ビジネス・映画産業に革命をもたらし、映像文化の礎を築いたのです。しかし近年では、韓国や中国、欧米企業の台頭により、プロジェクター市場における日本の存在感は相対的に薄れてきました。技術力は依然として高いものの、製品展開や市場戦略において主導権を握る機会は限られていました。
2025年大阪・関西万博は、こうした状況を打破する絶好の契機となります。三面スクリーンをはじめとする没入型映像体験の舞台で、日本の光学技術、映像演出力、そして素材開発力が再び世界の注目を集める可能性を秘めています。特に、光学薄膜や高精度投影技術においては、日本企業が蓄積してきた知見と製造技術が圧倒的な優位性を持っています。これらを映像体験の中核技術として再定義し、万博を通じて世界に発信することで、日本は再びプロジェクター技術の覇権を握る未来を描くことができるでしょう。