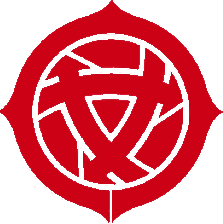関西万博×光学薄膜 Episode:3
宇宙開発が求める光学薄膜 ― 関西万博から未来へ
【1】宇宙開発と光学薄膜の交差点
2025年の大阪・関西万博では、「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、宇宙開発をはじめ多様な最先端技術を紹介していますが、「アメリカ館」や「ガンダムパビリオン」をはじめ、複数の展示が“宇宙”をテーマに据え、来場者に地球外世界の臨場感を体験させます。これらの演出は単なるエンターテインメントにとどまらず、実際に加速しつつある宇宙探査や宇宙産業の潮流と深く結びついています。
現在の宇宙開発は、従来の人工衛星や探査機運用に加え、深宇宙探査・月面基地建設・火星有人飛行・宇宙資源採掘・宇宙太陽光発電といった多様なミッションへと拡大しています。これらの計画の多くは、可視光・紫外線・赤外線といった幅広い波長領域の光を高精度に制御する光学技術を必要とします。その中でも、光学薄膜は観測機器・通信装置・エネルギー利用システムを支える基盤技術です。
光学薄膜とは、数nm〜数µmの厚みで屈折率の異なる材料を多層に積層し、干渉効果によって特定の波長を反射・透過・吸収させる構造を持つ機能膜のことです。衛星搭載カメラのバンドパスフィルターや宇宙望遠鏡の反射ミラー、防眩・防汚コーティング、太陽電池パネルの反射防止膜など、その応用範囲は広大です。しかし、宇宙空間は地上とは全く異なる極限環境であり、光学薄膜は次のような苛酷条件にさらされます。
✅ 宇宙線や高エネルギー粒子による放射線劣化
✅ -170℃〜+120℃以上に及ぶ急峻な温度サイクル
✅ 原子状酸素(AO)や微細な宇宙塵による物理・化学的損傷
✅ 打ち上げ時の振動・衝撃による機械的応力
このため、宇宙用光学薄膜は単なる波長特性の最適化にとどまらず、材料選定・膜構造設計・成膜プロセス制御のすべてにおいて、耐環境性と長期安定性を両立させる高度な技術が不可欠です。特に、真空中でのアウトガス抑制や、ナノスケールでの膜密着力強化などは、宇宙ミッション特有の課題として近年注目を集めています。こうして、関西万博が象徴的に描き出す「宇宙の未来像」は、光学薄膜を含む精密光学技術の進化と直結しており、その発展は次世代の宇宙活動の成否を左右する鍵の一つとなります。

【2】宇宙環境が求める光学薄膜の機能(技術編)
宇宙空間は、光学薄膜にとって極限の試験場です。真空中での揮発や膜剥離、放射線による結晶構造変化、熱サイクルによる応力集中など、地上とは桁違いの負荷が加わります。そのため、以下のような高度な設計・成膜技術が必要です。(※下記に参考事例を示しますが、当社での実績によるものではございません)
① 広波長域対応
紫外線(100〜400nm)から赤外域(2〜5µm、場合によっては10µm以上)まで高透過/高反射性能を維持するため、SiO₂などの低屈折率材とTiO₂などの高屈折率材での誘電体多層膜が採用されます。設計では、膜厚をλ/4または非整数倍に調整し、干渉条件を最適化。広帯域化には二重または三重の干渉系が有効です。
② 耐放射線性
宇宙空間における光学薄膜は、特に耐放射線性が重要視されます。宇宙線や紫外線の照射により膜内部の欠陥密度が増加し、屈折率の変動が生じるため、これを抑制するためには高密度な成膜技術が不可欠です。具体的には、イオンアシスト蒸着やイオンビームスパッタリングといったプロセスを用いて空隙率を低減し、膜の密度を高めることが行われます。また、酸化膜の非化学量論組成を調整し酸素欠陥を抑えることや、光学特性に影響を与えない範囲で薄い金属層を挿入して放射線を吸収する設計も採用されます。
③ 極端温度耐性
さらに、宇宙の過酷な温度環境にも対応しなければなりません。月面や静止軌道では、マイナス170度からプラス120度以上に及ぶ急激な温度サイクルが発生し、異なる熱膨張係数を持つ材料間に応力が集中します。この応力が原因で膜の剥離や微細な亀裂が生じることを防ぐため、成膜時には温度やイオンエネルギーを厳密に制御して膜応力を低減し、さらにSiO₂の緩衝層を挿入するなど応力緩和策を講じています。加えて、基板材料との熱膨張率を合わせる設計も重要なポイントとなっています。
④ 防汚・防曇機能
宇宙環境特有の防汚・防曇機能も求められます。真空中では樹脂や潤滑油から発生するアウトガスが膜表面に吸着し、光学性能の劣化を引き起こすため、フッ化物系のコーティング(MgF₂等)による低表面エネルギー化を施し、付着物の堆積を抑制しています。また、SiO₂トップ層の高密度化によって原子状酸素に対する耐性を強化し、ITOなどの帯電防止薄膜を表面に設けることで、静電気による微粒子の付着も防いでいます。
⑤ 軽量化と高耐久性の両立
最後に、宇宙機器の打ち上げ時には重量制限が厳しいため、光学薄膜の軽量化も欠かせません。膜厚を最適化して必要な干渉性能を確保しつつ層数を削減し、さらにナノラミネート構造を採用して機械的強度を維持しながら軽量化を図っています。樹脂基板を用いる場合は、高耐熱性かつ低吸水性の保護膜を成膜することで長期の耐久性を確保する技術も実用化されています。
このように、宇宙向け光学薄膜は単に高い透過率や反射率を追求するだけでなく、物理的・化学的な劣化メカニズムに対抗し、厳しい環境条件下で安定した性能を長期間維持するための総合的な設計・製造技術が求められるのです。
【3】宇宙で活躍する光学薄膜(実例編)
宇宙開発で用いられる光学薄膜は、用途ごとに波長域・耐環境性・質量制限が異なります。以下では、NASA・JAXAの実際のミッションや試作事例をベースに、代表的な応用例を紹介します。
① 衛星用バンドパスフィルター(地球観測)
✅事例:JAXA「しきさい(GCOM-C)」衛星
海洋色や植生状態を観測するため、400〜900nm帯の複数バンドパスフィルターを搭載。
✅技術ポイント
SiO₂(低屈折率)+Ta₂O₅(高屈折率)の多層干渉膜、±2nm以内の中心波長精度、打ち上げ時振動や温度サイクルに耐える低応力成膜
② 太陽光反射ミラー(耐UV・耐AOコーティング)
✅事例:NASA「SOHO」衛星や「Hubble宇宙望遠鏡」
太陽光や紫外線を反射するAlミラーにMgF₂またはAlF₃の保護膜を形成。
✅技術ポイント
アルミ基材に真空蒸着+保護膜成膜、原子状酸素(AO)耐性を付与、紫外域(<200nm)で90%以上の反射率維持
③ レーザー通信用ミラー/フィルター(衛星間光通信)
✅事例:JAXA「光衛星間通信実験機(OICETS)」
波長1.55µm帯を高効率に反射・透過する誘電体多層膜を採用。
✅技術ポイント:
HfO₂(高屈折率)+SiO₂(低屈折率)のλ/4多層構造、角度依存性を抑えるための非整数倍膜厚設計、±0.1%以内の透過率安定性(温度変化試験後)
④ 熱制御コーティング(サーマルコントロール)
✅事例:国際宇宙ステーション(ISS)の実験モジュール外壁
可視光を反射しつつ赤外放射率を高める多層薄膜(Optical Solar Reflector: OSR)が採用。
✅技術ポイント:
アルミナ基板+SiO₂多層膜、可視光反射率 > 85%、赤外放射率 > 0.8、紫外線曝露後も性能低下 < 2%
⑤ 惑星探査カメラ用ARコーティング
✅事例:NASA「Perseverance」火星探査車やJAXA「はやぶさ2」
搭載カメラには、400〜1000nmで反射率0.5%以下の広帯域ARコーティングを採用。
✅技術ポイント:
SiO₂、Al₂O₃、MgF₂の3〜4層AR膜構造、火星の低気圧・低温下での膜密着性確保、火山灰状の微粒子付着を抑える防汚トップコート
これらの事例から分かるように、宇宙用光学薄膜は単一の性能だけではなく、波長特性・環境耐性・機械的強度をすべて両立する総合設計が求められます。また、多くのプロジェクトでは地上での宇宙環境模擬試験(熱真空・放射線・原子状酸素曝露)を経て、初めて実機搭載が認められます。
【4】―未来展望― 宇宙産業と光学薄膜の拡張する役割
宇宙開発は今後、科学探査や通信だけでなく、資源利用・エネルギー供給・人類の恒久的な居住へと領域を広げていきます。それに伴い、光学薄膜には以下のような新しい役割が求められると予想されます。
① 月面・火星基地向けエネルギー制御フィルター
月面や火星の基地では、太陽光の有効利用と遮熱が重要課題です。可視光を効率的に透過させつつ、赤外域を選択的に反射して温度を制御する多層膜は、発電効率の向上と居住区の熱負荷低減に貢献します。
② 宇宙資源採掘用センシングフィルター
小惑星や月面での資源探査では、鉱物ごとの反射スペクトルを高精度に取得するため、広帯域かつ急峻なカット特性をもつバンドパスフィルターが必要になります。耐放射線性と防塵機能を兼ね備えた設計が必須です。
③ 宇宙農業・バイオ実験向け波長制御膜
植物の光合成に最適な波長(青色域・赤色域)を強調し、不要な波長をカットするフィルターは、月面温室や宇宙ステーションでの食糧生産において鍵となります。また、バイオ実験では特定波長での蛍光観測や殺菌にも薄膜が活用されます。
④ 自己修復型光学薄膜
将来は、原子状酸素や微小隕石による微細損傷を自動的に修復する自己修復材料とのハイブリッド膜が実用化される可能性があります。これにより、長期ミッションでも光学性能を維持し続けることが可能になります。
関西万博が描く宇宙の未来は、決して空想の産物ではなく、光学薄膜をはじめとする精密技術の延長線上にあります。残念ながら、本ページでご紹介した宇宙開発における具体的な光学薄膜の事例は、国内外のさまざまな企業や機関で開発されたものであり、当社(安達新産業株式会社)の製品ではありません。しかしながら、これらの先進技術が成熟し広がることは、私たちの技術開発の指針となるものであり、今後も光学薄膜分野で貢献してまいります。こうした技術の発展が実現すれば、人類は本当に地球外で持続的に暮らす時代を迎えることでしょう。